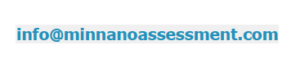その報告はウソだろっ!
インバスケット演習でいいたくなる気持ちもわかりますが…
今回のコラムもかなり短めで。
なんでしょう。最近、企業さん向けでの人材アセスメント、そのインバスケット演習で受講者の皆さん怒りっぽくなってますでしょうか?
何がといえばインバスケット演習の案件、つまり部下や関係者が報告・相談・依頼してきた内容について「それは嘘だ!」「そんな話がある訳ない!」「あなたの考えは根本的に間違っている!」「人として外れている!」
文面のホット感はあれこれですが、「だからこうしなさい」ではなく、その行為や考え違いに目くじらを立てて説教モード…。いったい何のコンピテンシーやディメンションの高評価を狙っているのでしょうか…。まさか正義感? その前に情報把握や問題認識、つまり理解や分析がマイナスの評価に。
中にはレポートラインの真上の部長、最上の社長に「その考えは間違ってます」と言い放つケースも。こういった場合「どこが違うの?」「なぜ違うの?」の理由は明示されず、同時に代替案の提示も不足するケースが散見されます。この直言居士の案件処理(理由や代替案がない)を見かけたアセッサー、かなりの確率で否定的な評価に突き進みます。
インバスケット演習のキャストは皆さん頓珍漢だけど…
今さらながら説明しますと、インバスケット演習で出てくる部下や関係者は不思議な意見の持ち主です。詳しくは以前の本コラムをご参照ください。
この頓珍漢なキャストに対して「それは嘘だ!」「そんな話がある訳ない!」「あなたの考えは根本的に間違っている!」「人として外れている!」といっても何もならないどころか同類に思われてしまうのでホント、注意が必要です。
だって言いたくなるの
インバスケット演習に解答する状況って圧力かかるし、時間がなくてアップアップしてる最中に部下のAさんから「おいふざけんなよ」といいたくなるようなメールが来ているといった設定、その矛先がAさんの能力に向かう気持ちは十分に理解しますが、かわいそうなAさん、ホントは高い能力の持ち主なのにインバスケット演習のキャストとなったばかりに頓珍漢なことを言わされる羽目におちいります。
なので賢明な受講者の皆さんは「だって言いたくなる気持ち」を押さえ、もっと別のアプローチを取るようにしましょう。
① Aさんはどこを勘違いしているのか?
② Aさんはなぜ勘違いしているのか?(能力が低いとかはダメ)
この付近がその案件のポイントになります。そしてそのポイントを何らかの表現で指示文や依頼文に織り込みましょう。そうすることで「理解」「分析」の評価アップにつながります。
③ Aさん、あるいはBさんやCさんに勘違いを正しつつ何らかの行動を依頼しましょう。
そうすることで「創造」「立案」の評価アップにつながります。
④ Aさん、あるいはBさんやCさんに何らかの行動を依頼、そしてこれを具体的なものに落とし込んでみましょう。
そうすることで「計画」の評価アップにつながります。
これは絶対ダメ!
「それは嘘だ!」「そんな話がある訳ない!」「あなたの考えは根本的に間違っている!」「人として外れている!」は論外ですが、これも絶対ダメなものとしては下。
⑤ Aさんが勘違いしているのか正しいのかわからないので「一度、確認してください」「もう一回、調査しておいてください」
・・・Aさんに頓珍漢なことを言わせる、つまり勘違いをさせたソコ! それがその案件のポイントなんで、返ってこない回答に逃げてしまうってのはもったいないの一言です。
社長や部長が頓珍漢な場合は?
案件の中での発言で、何かを見落としていたり、勘違いをしていたりってことを仕込むキャストは基本的に部下や関係者が多く、社長や部長の発言や意向に対してNOを突き付けることは避けましょう。
そうはいっても、社長や部長は自身の考えにこだわったり、時代遅れの方向性を示したりするわけです。それに対して違和感を覚えたとしても、まずはその違和感は横において達観して考えてみましょう。
「その自身の考えや時代遅れの方向性が事業低迷、組織迷走の要因では?」
「これが方針策定の前提条件では?」
前者は社長や部長の考えを非、後者は是として取り扱っています。どちらに則って案件処理や方針立案を進めていくかですが、現状、他の業者のインバスケット演習を含めた場合、前者は少なく、後者が一般的になっています。
事業低迷、組織迷走の根本的な要因はトップの方針が不明確であったり、あるいは朝令暮改的であったり、過度に一般論的であったりが現実ですが、インバスケット演習で出てくる企業・事業・部門・チームは、そもそも事業低迷、組織迷走として設定されています。なので、その要因を「社長や部長の考えが非であるから」としてしまう思考はムリがあるといわざるを得ません。
インバスケット演習で仮に全社方針的なものについて当該与件企業のトップが発信していたとすれば(大概、案件①で発信)、それはその与件企業の方針や課題を考える際の前提や制約として捉えていきましょう。
大きく逸脱、あるいは抵触しない範囲であらたな下位方針・事業方針・部門方針を立案したり、課題を見極めたり、施策を立案したり…。
一方、インバスケット演習の中には全社方針的なものをトップが発信していないケースもあります。その場合はどうするのか?
恒例ですが「続きは合格セミナー」の質問タイムをご活用してください。