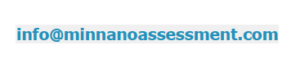しつこい人?あきらめない人?
面談演習であきらめない人
時節柄、今回も短いコラムでよろしくお願いいたします。
さて、面談演習であきらめない人ですが体感的な確率で約90%でよろしいでしょうか?
何をもってあきらめない人かですが、とりあえずは10分間、最後まで部下の説得をあきらめずに面談を続けます。残り約10%の受講者の方は「こんな面倒くさい部下の説得はムリ!」「だけど最後まで続けなければ」の責任感で「では次回、お話をすることにしましょう」という謎設定で時間を稼ぐというか、後退りしながらパンチを繰り出すというか…。
この「謎設定(後退りパンチ)」の受講者の方、減ってはいるけど未だ信じ込んでいる様子の方もいるので注意が必要です。
グループ討議でしつこい人
グループ討議でしつこい人ですが体感的な確率で約10%でよろしいでしょうか?
何をもってしつこい人かですが、グループ討議のケーススタディが競争タイプの場合、自分に振られた何某かの推し、例えば予算獲得とか部下推薦とかを通すことにあからさまにしつこい人、少数派である約10%となっています。
「競争タイプのグループ討議の場合であっても最善解を目標に基本、譲り合いの姿勢で討議を進める」という謎設定が未だ効いているのでしょうか?
面談演習の謎設定の信奉者が約10%、グループ討議の謎設定の信奉者が約90%になっている背景には、譲り合いや協調を美徳とする組織文化、あるいは同調圧力が働いているのかもしれません。
インバスケット演習であきらめない人、しつこい人
インバスケット演習であきらめない人ですが体感的な確率で約90%でよろしいでしょうか?
2時間~3時間の演習時間、最後まで手を止めずに鉛筆を走らせる、キーボードを叩き続ける、「ぴぴー、はーい、終了でーす」の掛け声とともに大きな溜息、机に突っ伏す、がっくし肩を落とす、とは言え最後までやりきったという虚脱感と恍惚感ミックスの微妙な表情で解答用紙を係に手渡す、あるいはシステムの採点ボタンを押下する…。中には終了時刻の20分前から余裕の表情でトイレに向かい、喫煙所で吹かす吹かす。けど解答用紙は半分程度の記入、吹かす仲間に「いやー、あんなもんじゃない?」「インバスケット演習ってなんか意味があんのかね?」「久しぶりに頭より手を使わせていただきました」「そんなこと自分で考えろっていいたくなるメールばっかりだったよね」などなど。
前者のあきらめない人は若手クラスで多くというか若手クラスは100%あきらめない人、後者のいろいろをあきらめてしまっている人は部長クラスで20%といったところでしょうか?
インバスケット演習でしつこい人って?
体感的な確率を宣するには母集団が少なくてなんですけど、インバスケット演習でしつこい人ってあきらめない人の中に確かに存在します。
ただし単純に「演習時間の最後までアウトプットをあきらめない人」ではなく、「全ての案件に解答しなくてはと頑張る人」の中に。けれど、頑張る人=しつこい人は言い過ぎといえば言い過ぎです。
この頑張る人、頻繁に見かける解答の構造ですが、例えば20案件あるインバスケット演習で「案件№7と案件№16の内容がほぼ同じになっている」「案件№8に『案件№5に書いたとおりです』と書いてある」となっており、同じことを繰り返し書いてしまっているので、しつこい人ですねと呼ばれてしまいます。
インバスケット演習で観察・評価するコンピテンシーは基本的に思考クラスターなので、あきらめないスタンスが直接、高評価に結びつくことはありません。
一方、このしつこいスタンス、つまり「同じことを繰り返し書いてしまっている」についても、直接、高低の評価に結び付くことはありません。
ただし、「同じことを書かなければもしかしたら高い評価になる」「同じことを書かなければムダな時間を費やすことがなくなる」の可能性、つまりメリットがありますよが今回の提案です。
同じことを繰り返し書いてしまっているという事象について、もう一度、よく考えてみませんか?
この要因としては以下が挙げられます。
① 同じことを書いてしまった案件№にはリンク(関連性)が貼り付けられている
② 同じことを書いてしまった案件№相互は課題レベルで同様の課題について記述してある
この①か②、あるいは①と②を前提として、全ての案件に解答をしなければならないの強迫によってこの事象は発生しています。
インバスケット演習の作成者として、あらためて受講者の皆さんにメッセージです。
異なった案件№に同じことを書かせるようなインバスケット演習を設計・作成するなんてありえません。限定的な時間の中で受講者の方に多くの証拠物件を書いていただきたいがニーズであり、そんなムダなことを受講者の方に強いるなんて…。
なので、同じことを書いてしまった場合、そこで自らを検証してください。
<Aパターン>
・案件№7と案件№16はどっちが主でどっちが従なのか?
・従と判断した案件7(対応を求められていない・期日がきられていない)、これを書いていては時間のムダなので思いきりよくネイキッドで提出する
<Bパターン>
・〇〇〇〇で▲▲▲
・✕✕✕なので◎◎◎◎
<Cパターン>
・✕✕✕なので◎◎◎◎
・〇〇〇〇で▲▲▲
…申し訳ございません。今回のコラムですが興奮していたので、つい肝心要の肝心まで書いてしまいました。要である<Bパターン><Cパターン>については、また合格セミナーで受講者の皆さんと一緒に確認を進めましょう。