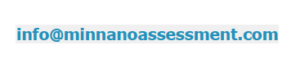人材アセスメントで高い評価を得るために
陸上競技ではなくフィギアスケート
時節柄短めのコラムとなります。
先日、大人数を対象にした人材アセスメントを実施しました。今回は昇進・昇格をかけた重要な回だったこともあり、受講者の皆さんの熱量はひときわ高いものでした。人懐こい方や物怖じしない方も多く、日程が終わるたびに質問が相次ぎました。
「私、合格しましたか?」
「何点くらいの成績でしたか?」
「今年度こそ合格したいので、よろしくお願いします」
お気持ちはよくわかりますので、私も精一杯の対応を心がけました。
「頑張ったよね」「点数はこれからだからね」「(にっこり笑って肩ポン)」
買収なり、リップサービスなり、人間関係作りなり
買収なんて大げさというか、あってはならない話ですが、リップサービスや人間関係構築を意識する受講者の方が一定数いるのも事実です。皆さん、何となくこうした“裏の構造”を察しているのでしょう。
なぜなら、人材アセスメントは、電子計測やビデオ分析といった客観的なシステムではなく、「人間」が評価を行っているからです。
巷では見てきたような色々な噂が飛び交っていますが、人材アセスメントはアセッサーが建前上、一次評価を実施した後、評価会議(アセッサーミーティング)で全アセッサーとリードアセッサーで最終評価を実施します。その一次評価も最終評価もデジタルではなくて超アナログ、アセッサーのこれまでの数少ない経験と自分だけの歪んだロジック、そしてリードアセッサーの昭和時代のマネジメント像と思い込みと言う名の直感で粛々と進められます…
私たち人材アセスメント業者は「絶対評価」であることを強調しますが、実際には相対評価、いや、むしろ“感覚評価”と表現したほうが近いのが現実です。
それでも受講者の皆さんは
それでも受講者の皆さんは、そんな信じ難い現実を前向きに受け止め、目前のアセスメントに臨む必要があります。そこで、今回のコラムのメッセージです。
「審査員が何を見ているのか」を意識して受講してください。
評価の対象となる「コンピテンシー」は事前に公開されていますが、実際にそれを強く意識して臨んでいる方は少数です。
「いやいやちゃんと意識してますよ」
「では、その意識はどんな形で表現されていますか?」
「え? 表現って、どういうことですか…?」
このように審査員が評価すると事前に開示しているコンピテンシー、それに対する問題意識というか工夫がないままエイヤーで受講している皆さんが多数派です。
工夫の仕方
この工夫の仕方ですが、まずは各演習でどのコンピテンシーを見るのか押さえておいてください。
・インバスケット演習では思考のコンピテンシーと決断(果断性)
・面談演習では資質のコンピテンシーと対人のコンピテンシー、中でも「部下育成」や「コーチング」
・グループ討議では対人のコンピテンシー
・方針立案演習では思考のコンピテンシーの未来創造系
これを前提とすると、インバスケット演習で挨拶や配慮、部下育成を意識した指示などは意味がないことがわかります。また、面談演習やグループ討議で分析や計画(段取り)を意識したところで大差ないことがわかります。方針立案演習で分析のフレームワークに一生懸命になることの愚かさも明らかですね。
そして肝心要の話、人材アセスメントは陸上競技ではなくフィギア、つまり審査員がいるので、審査される項目をしっかりとプレゼンテーションすることが大切です。人材アセスメントは陸上競技ではなくて「物まねコンテスト・顔まね部門」、つまり審査員がいるので、審査される項目(顔まね)をしっかりと演じてくださいってことです。ステージで歌のまねっぷり、フリのまねっぷりを頑張ってもらっても全く意味がありません。
もう少し続けると、インバスケット演習では「理解が得意」「分析ができる」「計画がプロ級」「創造はかなりなもの」「決断は『ほらこんなに』」を解答で示してください。面談演習では部下と一緒に部下の抱える問題を自らが当事者として解消していくことを演じてください。グループ討議では自分の得意な対人キャラクターをここまで出来ることをアセッサーに教えてあげてください。方針立案演習では新しいビジネスを構想することが抜群であることを報告書で示してください。
人材アセスメントの各演習で「普段からしている良い仕事」を再現しても全く意味がありません。私たちアセッサーは「良い仕事のプロ」ではなく、単なる「コンピテンシーの審査員」です。
受講者の皆さんは、普段の「良い仕事」を再現しようと一生懸命ですが、私たち審査員が見ているのはそこではありません。フィギュアスケートの審査員がジャンプの完成度を見るように、物まねコンテストの顔まね部門の審査員が「どれだけ似ているか」を見るように、私たちは「決められたコンピテンシーを、どれだけ表現できているか」を評価しているにすぎません。
フィギュアの場面では「まずはジャンプする」。物まねの顔まね部門では「まずは顔を寄せる」。その基本中の基本が抜け落ちたまま受講している方が、実はとても多いことをお伝えさせていただきます。